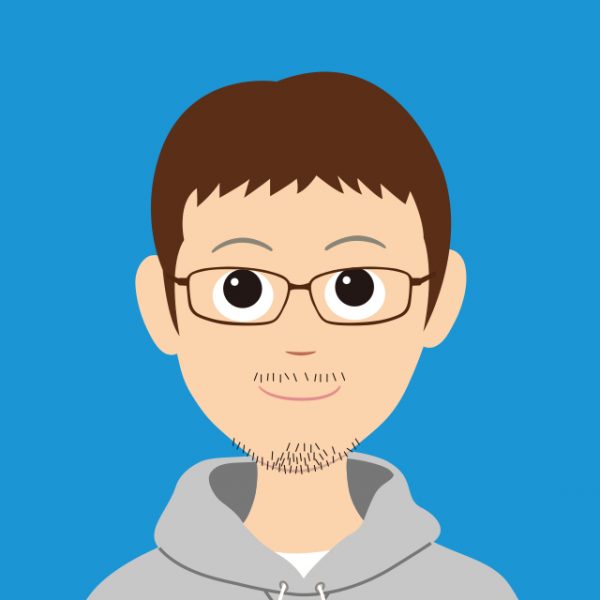【知っておいて損はない】サクッとわかるビジネス教養 行動経済学【おすすめ書籍】
書籍紹介
サクッとわかるビジネス教養 行動経済学
本書を選んだ理由
行動経済学の本を探していたところ、とっつきやすそうなこの本に出会いました。
なぜ行動経済学について勉強しようと思ったかというと、キンコン西野氏が勉強するべきといっていた言葉が頭にずっと残っていたからです。
経済学とかマーケティングとかは、理系で技術屋の自分には関係も興味もない分野という位置付けでした。
でも、なんか気になる感覚、そして、自分で壁を作らずに広く浅く学ぶことも大事かもしれないと考えて、購入してみました。
オールカラーでイラスト多めなので、私のような初心者でも読みやすそうと思ったのも選んだ理由の一つです。
著者 阿部誠さん
著者は阿部誠さん。
東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授。
1991年マサチューセッツ工科大学博士号取得後、2004年から現職。
2003年にJournal of Marketing Educationからアジア太平洋地域の大学のマーケティング研究者第1位に選ばれる。
こんな方へ
行動経済学って何?
という方。読んでみてください。
理系の人間には関係ないでしょ?
と思っていた私のような人にこそ読んで欲しいです。
人間の行動心理について理解を深められます。
目次紹介
第1章 基礎から学ぶ!知って得する行動経済学の考え方
第2章 人間らしい心の動き ヒューリスティック
第3章 意思決定の仕組み プロスペクト理論
第4章 マーケティングに活かす!行動経済学の活用事例
第5章 行動経済学の目玉!ナッジ理論
第6章 ビジネスで役立つ!行動経済学の応用法
要約
行動経済学とは
本書より以下に文章抜粋すると、行動経済学とは、
人間が必ずしも合理的に行動しないことに着目し、人間の心理的、感情的側面の現実に即した分析を行う経済学のこと
非常に実践的な理論が多く、政策にも活用されているほか、新型コロナウイルス対策の専門委員会のメンバーにも、日本の行動経済学の権威が任命されているほど
とのことです。
わかりましたかね?
たとえば、
好きな芸能人が紹介していた商品だからと、気になって買ってしまう
→非合理的な選択
本当は安いワインなのに、いかに高級かという説明を受けて信じてしまうと、高級ワインだと錯覚し、満足してしまう
→本当に高級ワインなのか確認できていない
1000万円の車が今なら700万円という広告を見て、安い!購入しようかな?と思ってしまう
→700万円という金額はそもそも大きな金額
など。
誰でも思い当たるケースがあると思います。。
私たちは普段、合理的に判断、選択を繰り返しているつもりでも、後から後悔するような選択をしてしまうことがたくさんあります。
行動経済学は、人は必ずしも合理的な行動をするとは限らないとし、合理性に加えて、感情も影響するという考えのもと分析を行い、「行動経済学=経済学+心理学」というふうに表現されます。
私は、体型維持のために毎日筋トレしているにも関わらず、お菓子やスイーツをばか食いしてしまいます泣
これも合理性に欠ける行動ですね。
行動経済学で分析されている、人間の習性について学んだ方が良さそうです。
以下に、本書で紹介されている人間の心の動きについて概略を説明したいと思います。
初頭効果、ピークエンドの法則
人にいい印象を残すために知っておくといい法則です。
まず、初頭効果。
これは、第一印象がその後もその人の印象として残りやすいというものです。
これは多くの人が本能的に意識しているように思います。
初対面の人との挨拶、自己紹介の印象は残りやすいことを念頭に、相手の目を見たり、ハキハキ話すことを心がけた方が、相手にいい印象をもってもらえ、後々のコミュニケーションも円滑になりやすいです。
次にピークエンドの法則。
これは、初頭効果とは逆で、最後の印象が良いと、その印象もずっと残りやすいというものです。
たとえば、プレゼン後の挨拶や、退職時の挨拶など。
最後の挨拶までに紆余曲折あったとしても、最後をビシッと決めることで、いい印象を持ってもらえるそうです。
私は、つい最近、退職にあたってこれまでお世話になった方々にしっかり挨拶してきましたので、これは大丈夫かなと勝手に思っていたりします。
最初と最後が大事!
ハロー効果
人は、目立ちやすい特徴に引きずられて、他の特徴についての正確な評価を怠りがちになること
たとえば、
有名人が紹介しているからこの商品良さそう!買ってみよう!
商品についてはちゃんと理解、評価した?
→好印象な有名人の影響で商品もよく見えてしまう
私が体験したハロー効果は、前職の人事担当の方々が爽やかイケメンと美人さんでしたので、その会社もよく見えました。そして入社(それだけの理由ではないです)。
何か自分の武器があると、他の欠点もハロー効果で補えそうですね。
目立つ特徴で相手の脳内をいっぱいにする
プラシーボ効果
自分が好きや正しいと感じたことを肯定するため、認知バイアスが働く
たとえば、1000円のワインを1万円のワインと説明を受けてそのワインを飲むと
さすが高級!美味しい!
と思い込んでしまう。
人間の脳は値段が高いと知るだけで、本当に美味しいと思い込み、満足してしまいます。
実際に高額な食べ物やダイエット食品が、この効果で高い満足度を得ているケースは多いそうです。
人は、脳が思い込んでしまいさえすれば満足する
サンクコスト効果
投資した労力、時間、お金を「もったいない」と考え、損するとわかっていても辞められない
たとえば、パチンコをしている人が
ここまで10万円も注ぎ込んだのにここでやめるわけにはいかない!
と考えるようなケース。
※これまでに費やしてきた時間、お金、労力はこれからの当たる確率には影響しません。
会社を長く勤めるほど辞めづらくなる心理も、サンクコスト効果があるのかなと思いました。
毎日、会社生活に人生の多くの時間を投入する分、得られた経験や人との繋がりを考えると、そのことに固執しそうになるかもしれません。
本当は理不尽な労働環境だと理解していたとしても。
私はいろんなしがらみを断ち切りました。
人は過去の労力にこだわりがち
大切なのは今、そして未来
アンカリング効果
最初に提示された情報がのちの判断に影響を与えること
たとえば、
この車1000万円のところ、今なら700万円です!
安い!買おう!
落ち着け!
こんなケースです。
最初に提示された1000万円が基準(アンカー)となり、700万円が安く感じてしまうのです。
700万円、安くはないですよね。
その他、仮に700万円の車を購入するとして、数万、数十万のオプションは誤差と感じてしまい、躊躇なく追加購入してしまったりも、アンカリング効果と思われます。
落ち着け
フレーミング効果
表現の仕方が変わると、与える印象も変わる
たとえば、
タウリン1g配合
タウリン1000mg配合
後者の方がタウリンがたっぷり入ってそうですよね。本当は同じ量なのに。
言葉の表現の違いで、受け取る印象は変わってきます。
何かアピールしたい場合は、フレーミング効果を意識して、インパクトを与えましょう。
言い方で損してない?
プロスペクト理論
人は得より損に過大評価してしまう
たとえば、
100%100万円もらえる or 50%の確率で200万円もらえる
この選択肢だと、前者を選ぶ人が多い傾向になります。
期待値的にはどちらも100万円もらえますが、後者は50%の確率で0円となりますので、その損を回避したいと人は考えます。
何か商売や交渉で相手に選択肢を与える場合は、損が少ない方を選ぶことを頭に入れておくと、自分の思うように話が進むかもしれません。
リスクってこわいよね
感想
行動経済学の内容について、かいつまんで紹介しました。
私たちは頭で考えて、自分の意思で、日々、選択を繰り返している気がしていますが、意外と合理性に欠いた選択も多くなりがちということがわかりました。
本書を読んでいると、確かに頭ではよくないとわかっていても、後悔するような判断をしてしまうケースがたくさんあることに気づきます。
今後は、その場その場での、衝動的な判断には気をつけて、後悔のないように注意していきたいと思いました。
また、仕事柄、営業や販売の職種ではないため、本書で紹介された判例を実践する機会はないのですが、何か応用できることがあれば試していき、結果報告もできればと思います。
本書には他にもさまざまな法則や効果が書かれています。
要チェックです!
著者の他の著書
最近の書籍紹介1

最近の書籍紹介2